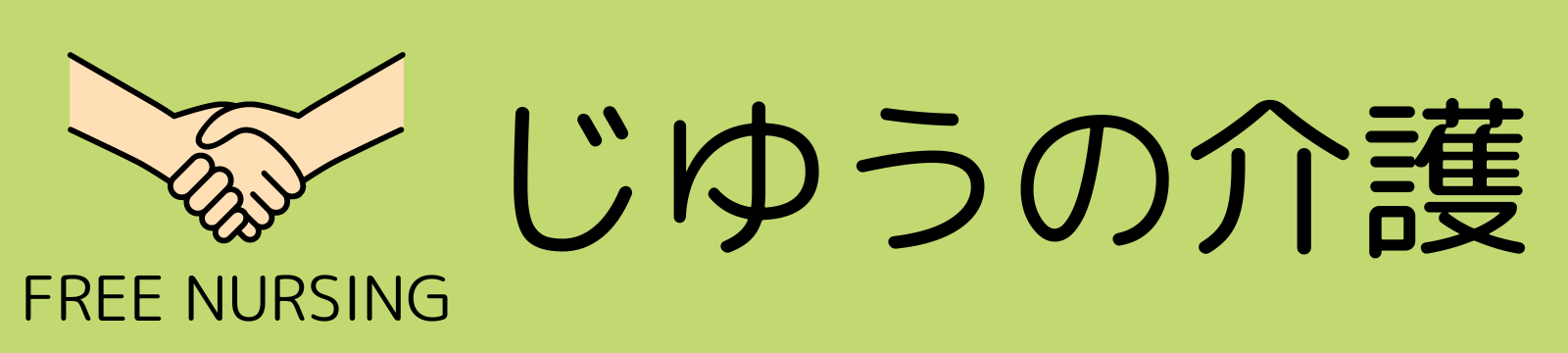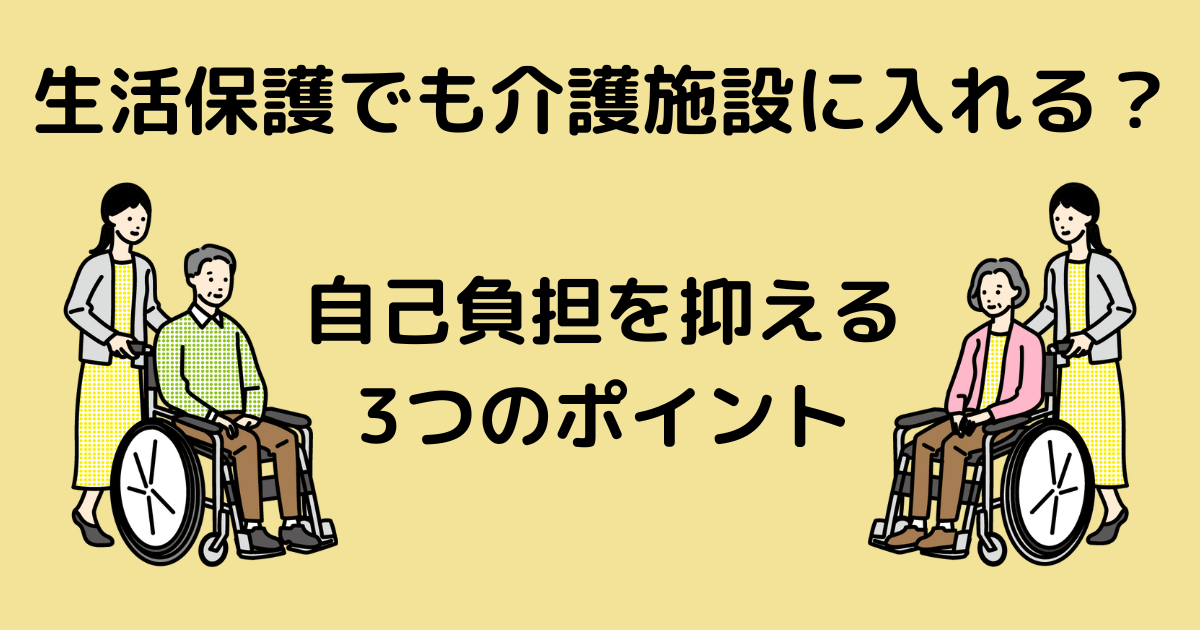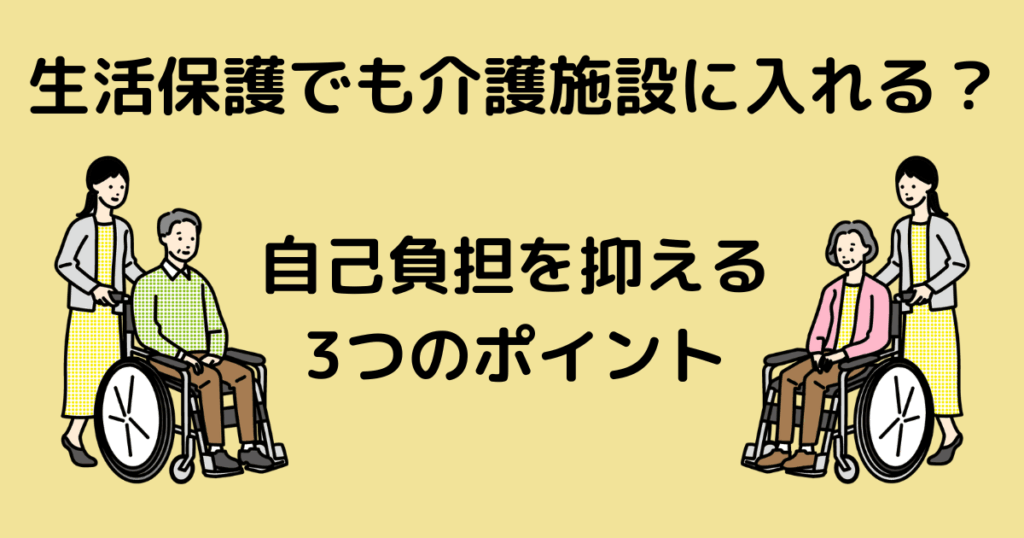
 くるみさん
くるみさん生活保護を受けている親が介護施設に入ると、子どもに費用が請求されることはありますか?



原則として介護費や居住費・食費は生活保護の範囲でまかなわれます。
ただし、自費サービスや日用品費などは自己負担となる場合があるため、契約内容を事前に確認しておくことが大切です。
生活保護を受けている親が介護施設に入居するとき、「そもそも入れるのか?」「子どもに費用を求められるのでは?」と不安を抱く方は少なくありません。特に、親の自己負担が生活保護の範囲内で収まるかどうかは、多くの家族にとって心配事です。
この記事では、生活保護を受けながら安心して介護施設を利用する仕組みと、自己負担を抑えるための制度やポイントをわかりやすく解説します。
生活保護でも介護施設に入居できるのか?


生活保護を受けていても、条件を満たせば介護施設への入居は可能です。経済的な理由で介護サービスを諦める必要はありません。介護保険制度と生活保護制度は併用でき、介護が必要と認定された方は生活保護の扶助制度を活用して施設を利用できます。
介護保険サービスの費用は「介護扶助」でまかなわれるため、収入や資産が少なくても公費でカバーされます。
ただし、一部施設では生活保護受給者の受け入れを制限している場合もあるため、入居前に福祉事務所などへ問い合わせておくとよいでしょう。
「生活保護を受けている親が施設に入ると子どもに費用請求がくるのでは」と心配される方もいるかもしれません。介護保険サービス費用や居住費・食費は生活保護でまかなわれますが、施設によっては入居時に家族へ身元引受人や連帯保証人を求める場合があります。
この際、生活保護でカバーされない自費サービスや日用品、居室の破損費用などが家族に請求される可能性があります。未払いが続くと退去を求められることもあるため、契約内容は事前に施設へ確認しておくと安心です。
自己負担額を生活保護の範囲内に抑える方法
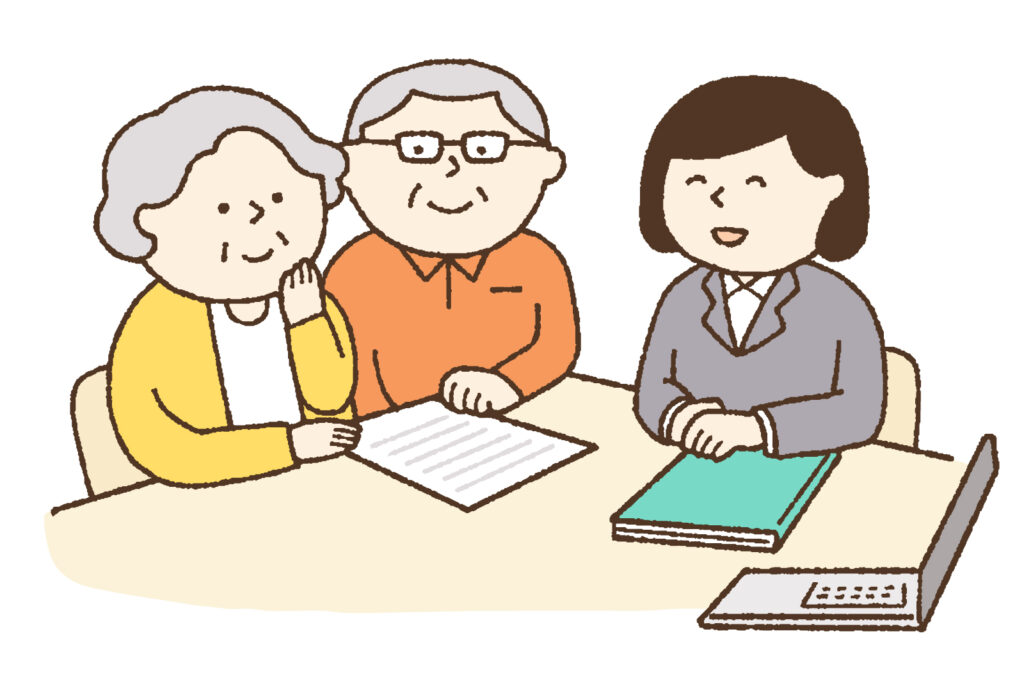
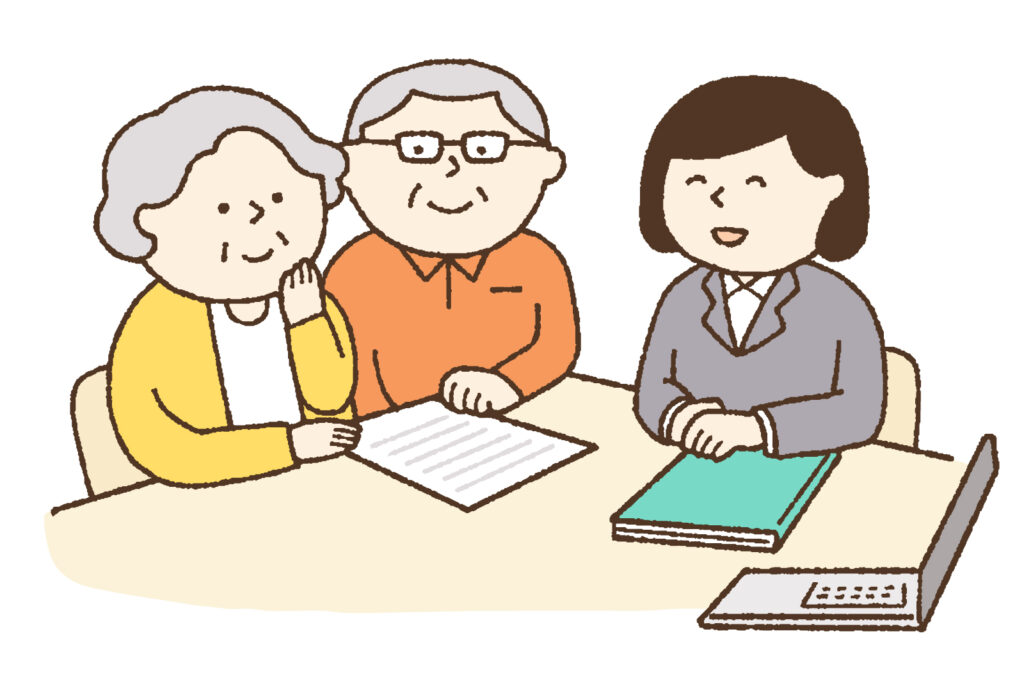
生活保護を受けている方でも、制度を上手に活用すれば介護施設の自己負担額を最小限に抑えられます。ここでは、費用を受給額内におさめるための主なポイントを紹介します。
- 地域の住宅扶助の上限を調べる
- 費用を抑えた施設を探す
- 地域包括支援センターに相談する
生活保護で入居できる施設を探す際は、住宅扶助の上限と施設費のバランスが重要です。
地域の住宅扶助の上限を調べる
生活保護には「住宅扶助」という仕組みがあり、地域ごとに家賃の上限が定められています。介護施設に入居する場合、この上限額内の施設でなければ、家賃が保護費から支給されません。
都市部と地方では上限額に差があり、例えば同じ単身世帯でも東京23区は約5.3万円、地方では約3.6万円といった違いがあります。
入居を検討する際は、福祉事務所やケースワーカーに『家賃が住宅扶助の範囲内に収まるか』を相談しておくと安心です。
参考1:宗健, 『博士論文(筑波大学大学院人間総合科学研究科)』, 2017年, 「生活保護住宅扶助費の市場家賃との比較および住宅選択行動」表 4-1
参考2:厚生労働省, 『第52回社会保障審議会生活保護基準部会資料』, 2025年, 「生活保護制度の概要等について」○P7各種扶助・加算の概要(令和7年4月時点)
費用を抑えた施設を探す
介護施設の利用料は、同じサービス内容でも種類や立地によって大きく異なります。中でも家賃部分は重要なポイントです。生活保護受給者を受け入れている施設の中には、家賃を抑えた部屋を用意している場合もあります。
特に、特別養護老人ホーム(特養)は公的施設で、入居金や保証金が不要なため、費用を抑えやすい傾向にあります。一方、有料老人ホームは民間運営のため、入居金や管理費が発生しやすく、施設によって費用差が大きいのが特徴です。入居前に複数の施設を比較し、無理のない範囲で選びましょう。
地域包括支援センターに相談する
どの施設が生活保護でも入居可能なのか分からない場合は、地域包括支援センターに相談してみましょう。介護保険や生活保護制度に詳しい職員が、利用者の状況に合わせて入居先を紹介してくれます。
施設探しだけでなく、手続きや扶助制度の申請もサポートしてもらえるため、自分で調べるよりスムーズに進められます。
生活保護でも利用できる代表的な介護施設
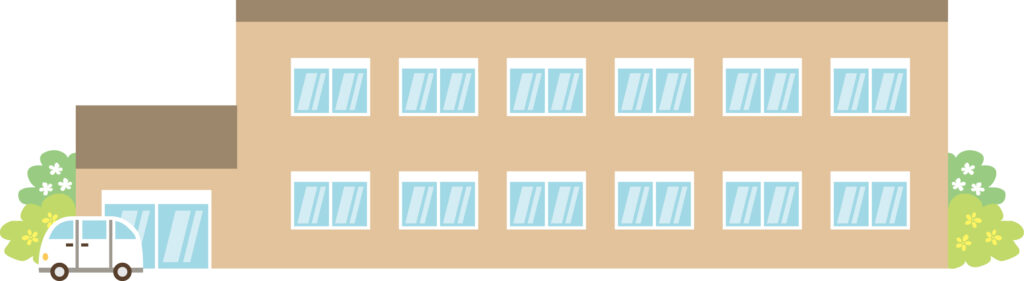
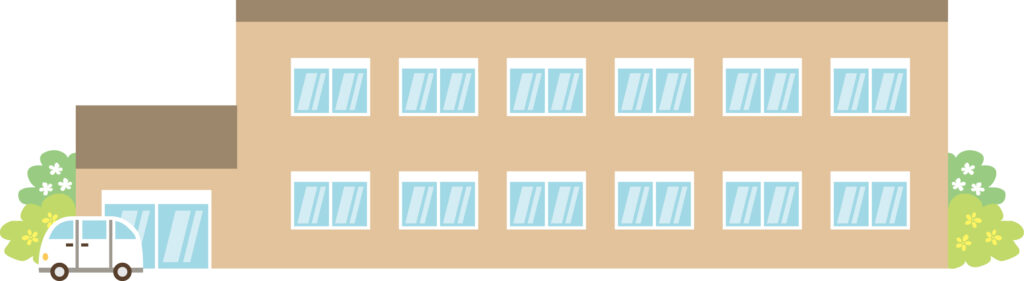
生活保護を受給していても、条件を満たせば入居できる介護施設はいくつもあります。ここでは、費用面で利用しやすい代表的な施設を紹介します。
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 有料老人ホーム
- グループホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
施設の特徴を理解しておけば、本人の状態や希望に合わせた選択がしやすいでしょう。
特別養護老人ホーム(特養)
要介護3以上の高齢者が対象となる公的施設で、生活保護受給者の入居も多く見られます。介護費用は「介護扶助」でまかなわれ、居住費や食費も「負担限度額認定制度」を利用すれば、ほとんど自己負担が発生しません。生活支援を中心とした環境で、安心して長期的に暮らせます。
有料老人ホーム
有料老人ホームは民間施設のため費用の幅が広く、すべての施設が生活保護に対応しているわけではありません。ただし、自治体によっては受給者でも入居可能な施設があります。入居一時金が不要で、月額費用が住宅扶助の範囲に収まる施設を選べば、自己負担を抑えられます。入居前に「生活保護受給中でも入居できるか」を確認しましょう。
グループホーム
グループホームは認知症の高齢者が少人数で共同生活を送る施設で、家庭的な雰囲気が魅力です。生活保護受給者でも、住宅扶助と介護扶助の範囲内で利用できる場合があります。食費や日用品費は一部自己負担となりますが、他の施設に比べると比較的安価です。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
サ高住は見守りや安否確認サービスが付いた賃貸住宅で、介護サービスは外部事業者を利用します。自由度が高く、家賃や共益費、生活支援費が発生しますが、家賃が住宅扶助の範囲内であれば生活保護でも利用可能です。介護度が低い方や自立した生活を望む方に向いています。
まとめ


生活保護を受けていても、条件を満たせば介護施設への入居は可能です。介護サービス費は「介護扶助」でまかなわれ、居住費や食費も「住宅扶助」や「負担限度額認定制度」を活用すれば、自己負担を最小限に抑えられます。
家族に金銭的な負担を強制されることはほとんどなく、生活保護の範囲内で安心して介護サービスを利用できます。費用を抑えるには、地域の住宅扶助の上限を調べ、生活保護受給者の受け入れに積極的な施設を探すことが大切です。困ったときは地域包括支援センターや福祉事務所に相談し、制度を正しく活用しましょう。
正しい知識と準備があれば、本人も家族も経済的な不安なく、安心して介護生活を送れます。